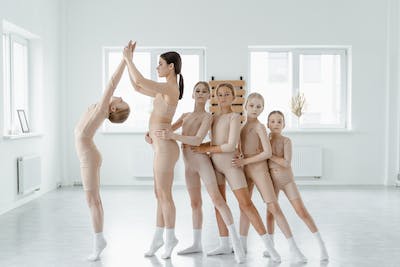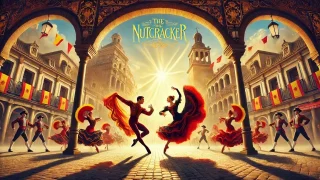【閲覧注意(バレエ好きの方)】『くるみ割り人形』の「スペインの踊り」が象徴するチョコレートの「闇」について

ものものしいブログタイトルとアイキャッチ画像で恐縮ですが、今回は『くるみ割り人形』の「スペインの踊り」の闇についてのお話しです。
踊りや演奏そのものにダイレクトに関係するものではないし、むしろ知ってしまったら気持ちよく踊ることができなくなる人もいると思うので、特に児童生徒は理解するのも難しいですし、今回は読まないほうがいいでしょう(笑)
ただ「スペインの踊り」が象徴とするチョコレートの苦い歴史と甘くない現実の話は、作品への理解が深まるはずなので、ご興味のある方は参考にしてもらえればと思います。
侵略・破壊の末にスペインに持ち込まれたチョコレート
前に別の記事
「なぜ『くるみ割り人形』の「スペインの踊り」はチョコレートを象徴しているのか?けっして甘くはない歴史的背景のある踊りのご紹介」
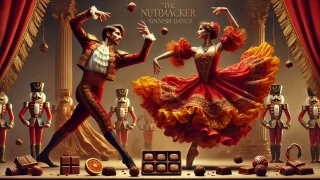
でもお話ししましたが、チョコレートの歴史には植民地時代の暗い側面も含まれています。
教科書や多くのブログなどでは
「チョコレートの原料となるカカオ豆が初めてヨーロッパに伝わった国はスペイン」
のように、サラッと書かれることが多いですが、結局のところ
スペインの征服者たちがアメリカ大陸を侵略し、現地の文明を破壊した過程で、多くの人々が命を落としましたという血みどろの歴史
がそこに横たわっています。
アステカやマヤの文化が持っていた豊かな伝統や知識も、征服と共に失われた部分が多いです。
気軽にチョコレートの甘さや美味しさを語るのもいいですが、歴史の中には光と影の両方があることは知っておいて損はないでしょう。
『くるみ割り人形』はおとぎ話の世界を描いていますが、そこに歴史的な背景を重ねることにより、作品の裏側には植民地時代の交易や富の不均衡が含まれていることを知ると、作品への理解がいっそう広がると言えます。

チョコレート産業に現代の帝国主義と貧困問題が潜んでいる
また、チョコレートにおける闇は歴史の一部ではなく、リアルタイムでも存在しています。
チョコレートという甘い嗜好品の裏側には、実は深刻な社会問題が隠れていることは、認識すべき重要な事実です。
その社会問題とは、アフリカの国々におけるカカオ慶園では、現代でも奴隷的な労働を強いられているという現実です。
西アフリカでのカカオ生産における児童労働や貧困問題は、世界的なチョコレート産業の構造的な不平等を映し出しています。
特に児童労働や強制労働の問題は深刻で、多くの子どもたちが教育の機会を奪われたり、危険な環境で働かされたりしているのです。
これは単に倫理的な問題にとどまらず、世代間の貧困の連鎖を生む要因にもなっていて、小規模農家が大部分を占めるカカオ産業では、農家の収入が不安定で、グローバル市場での価格変動の影響を強く受けるため、どうしても彼らが公平な利益を得るのは難しい状況です。
「スペインの踊り」が持つ異国情緒や華やかさを感じる一方で、その背後にあるカカオやチョコレートの歴史のみならず、さらに現代の課題にも思いを巡らせることは、ただ美しい音楽としてではなく、複雑な物語を内包した作品として深く味わえるかもしれません。

最後に
『くるみ割り人形』の「スペインの踊り」がもたらす明るさや楽しさを素直に受け止めつつ、その背景にあるチョコレートの歴史や現代の問題を知ると、また違った角度から作品を理解することができるものです。
芸術は、単に楽しむだけではなく、考えさせられたり行動を促したりするきっかけにもなりますし、「スペイン踊り」を通して様々な問題を考えながら、また『くるみ割り人形』の魅力を新たな形で楽しんでみてください。