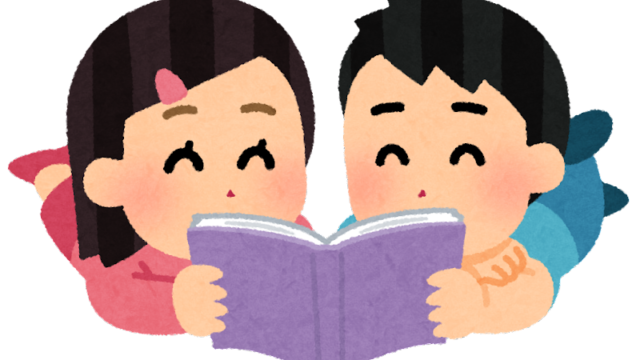『くるみ割り人形』の「ジゴーニュ小母さんと道化たち」が地味に使い勝手がいい曲である件について

今回は『くるみ割り人形』の「ジゴーニュ小母さんと道化たち (La Mère Gigogne et les Polichinelles)」に特化したバレエあるあるです。
『くるみ割り人形』の中でも、ある意味一番特異性のある曲と言えるので、その特徴をここでは3つに絞ってご紹介したいと思います。
プロのバレエ団ではカットされること多い
『くるみ割り人形』は、極めて完成度の高い作品で、『白鳥の湖』や『眠りの森の美女』と違い、曲の改変やカット、曲順の入れ替えなどの演出はあまり見ることのない珍しいバレエです。
オペラと違い、バレエというジャンルにおいては、プロデューサーや振付家の意向で、作曲者の意図を考えず作品を改変することも多いのですが、『くるみ割り人形』はチャイコフスキーが作曲した曲も順番もそのまま使用することが多いです。
ただ、その『くるみ割り人形』も一曲だけ例外があって、それが今回ご紹介する「ジゴーニュ小母さんと道化たち」です。
傾向的にヨーロッパのバレエ団ではカットされてしまうことが多いです。
演奏会用組曲版でも「スペインの踊り」とともにカットされてしまう末路をたどってしまいます。
個人的にはテンポ感のあるいい曲だし、コミカルな場面で楽しいところだと思いますが、カットされる理由としては以下の3つを挙げることができるでしょう。
子役が必要
「ジゴーニュ小母さんと道化たち」の一般的な演出は、大きなスカートの中から子供たち(ポリシネル)が次々と出てくる形になっています。
そのため成人したダンサーだけで公演するプロダクションだと子役がいないために、そもそも踊りとして登場させにくいです。
いくつかのバレエ団では、付属の学校の生徒に踊らせたり、バレエ教室に公募をかけて子役を募ったりしますが、それもバレエ団によっては手間となるでしょう。
フランス要素が重複する
「ジゴーニュ小母さん」はフランスの民話的なキャラクターですが、バレエ全体の流れを考えると「葦笛の踊り」だけでフランス代表として十分とも言えます。
一応2幕のディベルティスマンは各国の踊りという側面もあるので、フランスだけがもう一つ増えるのはバランスが悪いと考えることもできますね。
一連のディベルティスマンが長くなる
『くるみ割り人形』の2幕のディベルティスマンは6曲からなっていますが、その後の第13曲 花のワルツ (Valse des fleurs)が約7分間ぐらいにあるので、「ジゴーニュ小母さん」の曲を入れると、全体的に間延びしてしまいます。
他の各国の踊りも相対的に目立たなくなってしまうので、全体の流れを考えるとカットするのも一つの形と言えるかもしれませんね。
バレエ教室では児童クラスが大活躍する定番シーン
プロのバレエ団ではカットされがちな「ジゴーニュ小母さん」の踊りですが、日本のバレエ教室の発表会では幼児・児童クラスが活躍する場面で、むしろ絶対にカットされないところです。
「ジゴーニュ小母さん」のスカートから子供たちが出てくる設定なので、実際の子供が踊ることは役柄にそのまま当てはまっており、児童クラスをあてがうのは、理にかなっていると言えます。
まさに
「子供役を本物の子供が演じる」
という理想的な踊りなので、発表会は年齢に合わせて役を振り分けることが多いですが、この場面ほどピッタリなものはないでしょう。
児童クラスはまだリズムを取るのも難しく、なかなか踊れない子もいるし、動けない(動かない)子もいますが、子供たちの踊りはちょっとくらい不揃いでも、それが「かわいさ」として成立しちゃうから不思議です。
必ずしも「うまく踊る必要」はなく、もし大人バレエでやったら地獄絵図になるところも、子供ならマンガチックになり、実際の発表会でも常に笑いが起きる楽しいシーンですね。
演奏会形式では一番盛り上がる
『くるみ割り人形』の中で、「ジゴーニュ小母さん」の踊りは少し影が薄い存在かもしれません。
前述したとおり、プロのバレエ団ではカットされることも多く、ロシアやアラビア、中国などの各国の踊りと比べると知名度も控えめです。
しかし、演奏会形式になると話は変わり、客席を一気に盛り上げる“隠れた名曲”になることもあるんです。
全曲を演奏会で披露する機会はそう多くありませんが、第2幕のみを抜粋して演奏することは意外とありますし、アンコールで使われることもあります。
そのとき、「ジゴーニュ小母さん」の踊りは間違いなく最もボルテージの高い曲の一つとなります。
急激なダイナミクスの変化、カラフルなオーケストレーション、そして遊び心あふれるリズムが詰め込まれた、まるで音楽自体がじゃれ合うような楽曲です。
子どもたちが駆け回ってはしゃいでいるかのようなエネルギッシュな音楽で、特に、スタッカートが心地よく跳ねる部分は、まるでリズムの上を軽やかにスキップしているような気分にさせてくれます。
バレエの舞台では見逃されがちでも、演奏会ではしっかりとその魅力を発揮する「ジゴーニュ小母さん」なので、バレエの発表会でも音楽に耳を傾けてほしい曲です。
最後に
「ジゴーニュ小母さんと道化たち」は、他の各国の踊りの完成度があまりにも高いこともあって、存在が薄くなりがちです。
でも、緩急があって聞きごたえのある名曲なので、もう少し光が当たってもいいのかなと個人的には思います。
音楽もさることながら、バレエでも児童クラスにあてがうことができるので、汎用性の高い曲と言えるでしょう。
プロのバレエ団ではカットされがちな現状がありますが、もう少し表舞台で輝いてもいい曲なので、皆さんも「ジゴーニュ小母さんと道化たち」にはもっと注目して頂ければと思います。