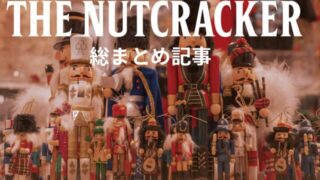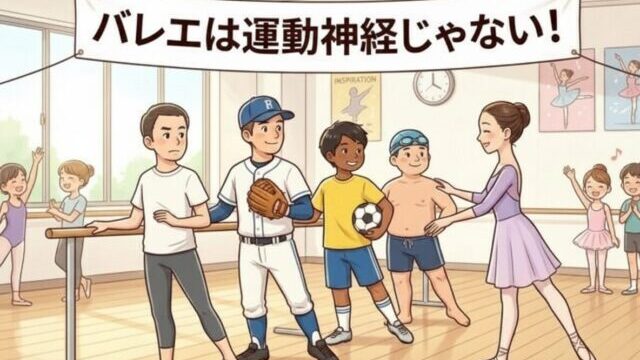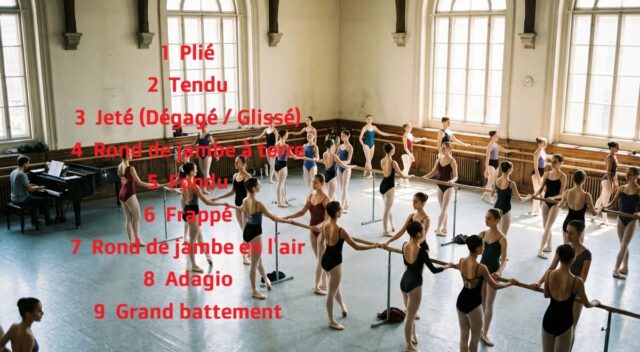『くるみ割り人形』第1幕で「熊」が踊る!ボストン・バレエ団の「The Nutcracker Bear」がすごい!

『くるみ割り人形』第1幕の第4曲《踊りの情景(Scène dansante)》の後半では、3体の人形たちが登場するヴァリエーションがあります。
最初の2つ(アルルカンとコロンビーヌ)は台本や作曲指示書に比較的明確な指示がありますが、3番目のヴァリエーションに関しては、台本にも作曲指示書にもはっきりとした指定がなく、振付家によってキャラクターが大きく異なるのが特徴です。
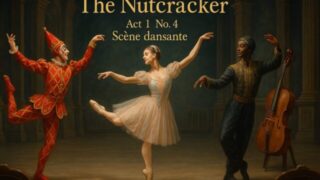
今回はその第3ヴァリエーションの中でも、最も有名なボストン・バレエ団の
The Nutcracker Bear
をご紹介します。
この「熊」の踊りは賛否両論もありますが、キレキレの踊りを毎回披露して観客を沸かせてくれますので、未見の方は動画と共に楽しんで頂ければと思います。
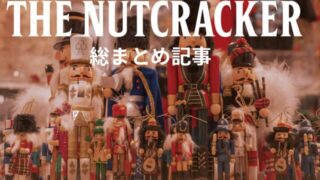
「The Nutcracker Bear」ってどんな存在?
ボストン・バレエ団が毎年12月に上演している『くるみ割り人形』。
そこに登場するこの熊は、正式には
「The Nutcracker Bear(ナットクラッカー・ベア)」
と呼ばれています。
1996年から舞台に現れ始めたこのキャラクターは、いまやボストン・バレエのマスコット的存在です。
子どもたちから大人まで幅広く愛されており、ぬいぐるみやキーホルダーなどグッズ展開もされていて、世界中にファンがいます。
でも、この熊の最大の魅力は「かわいらしさ」ではありません。
中に入っているのは、もちろんれっきとしたプロのダンサー。
ジャンプ・ターン・バランスなど、バレエの技術が詰まった超キレキレの動きを披露するのです。
動画サイトやSNSでは「キレキレに踊る熊」として話題になり、たびたびバズっているほどです。
この熊が登場すると、客席の子どもたちはもちろん、大人も一気に笑顔になり、劇場に特別な一体感が生まれるほどで、この「熊」だけのためにボストン・バレエ団の公演を見る人もきっと多いことでしょう。
「熊」の登場に賛否両論あるのも事実
このような演出については、当然ながら賛否両論もあります。
<否定的な意見>
「原作や古典の様式美を壊している」
「本来の文化的・象徴的意味が薄れる」
「子ども向けのショーアップに寄りすぎ」
特に伝統を重んじる一部の観客や評論家の間では、「こんなのはバレエじゃない」とする意見も聞かれます。
とりわけ、伝統を重んじるクラシック・バレエの中で、熊の着ぐるみが登場するというアイデアには抵抗感を示す人も少なくありません。
<肯定的な意見>
「観客層の拡大に貢献している」
「子どもたちのバレエへの入り口として最高」
「時代性・多様性を反映していてむしろ素晴らしい」
現代の舞台芸術は、エンターテインメントとしての役割も担っています。
観客が笑って楽しめる場面があることで、劇場がより開かれた空間になる――そんなポジティブな評価も根強いです。
そもそも、着ぐるみキャラの導入はボストン・バレエ団だけのものではありません。
たとえば英国のロイヤル・バレエ団でも、アシュトン振付の『ラ・フィーユ・マルガルデ(リーズの結婚)』や『ピーターラビットと仲間たち』などにユニークな着ぐるみキャラクターが登場しています。
つまり、「着ぐるみ=邪道」というのは一面的な見方とも言えるのです。
最後に:伝統と革新、そのちょうど間で
「The Nutcracker Bear」は、伝統的なバレエ作品に現代の感性を持ち込んだ例として非常に興味深い存在です。
確かに、『くるみ割り人形』はクラシックバレエの古典中の古典で、歴史や文脈を大切にすることはもちろん重要です。
でも同時に、観客に届ける「喜び」や「驚き」もまた、舞台芸術の本質。
それを見事に体現しているのが、この踊る「熊」とも言えます。
そんな伝統と革新の間に立ちながら、『くるみ割り人形』を楽しむのもいいかもしれませんね♪