アルルカンとコロンビーヌって何者??コンメディア・デッラルテ(Commedia dell’arte)とバレエの関係について

昔あるバレエ団の『くるみ割り人形』の公演を見ている時に、一つ前の席を陣取っていたバレエガールたちが
「アルルカンとコロンビーヌって、何の人形なの??」
とワイワイと盛り上がっていました。
確かに他のバレエ作品でもちらほら登場するだけに、何か得体の知れない謎な人達に見えなくもありません。
結論的にはアルルカンやコロンビーヌは
コンメディア・デッラルテ(Commedia dell’arte)のストックキャラクター
で、これは以前の記事でもご紹介しましたが、ここではもう少し詳しくお話ししたいと思います。
バレエのみならずオペラや現代演劇にも影響を与えたキャラクターたちで、『くるみ割り人形』を鑑賞する上でも知っておくと理解が深まるので、参考にしてもらえればと思います。
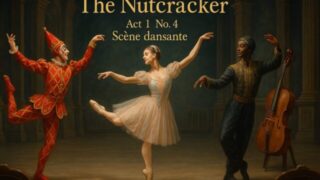
コンメディア・デッラルテ(Commedia dell’arte)とは?
コンメディア・デッラルテは、16世紀のイタリアで生まれた仮面を使った即興演劇です。
俳優たちは「アルルカン」や「コロンビーヌ」など典型的なキャラクターを、決まった型や衣装・マスクで演じながら、大まかなストーリーに沿って即興でせりふや動きを展開し、観客と双方向的に交流するのが特徴です。
この即興演劇に登場するキャラクターは、典型的でわかりやすい性格や特徴をもつので、その後のバレエやオペラや演劇の登場人物として使われるようになりました。
おなじみの「アルルカン」「コロンビーヌ」「パンタローネ」などは、バレエのみならず様々なジャンルで使われているのです。
物語ごとに名前や立場が多少変わることもありますが、一定の特徴や役割を持つキャラ造形は現在でもあらゆるジャンルで広く用いられています。
コンメディア・デッラルテの代表的なバレエ作品
『くるみ割り人形』の人形の踊り以外でもいろんなバレエ作品に、コンメディア・デッラルテのキャラクターは用いられています。
有名なところでは、次にあるものが挙げられ、現在でもたまに全幕上演されますし、一部の踊りはコンクールの定番ヴァリエーションとして使われたりします。
『アレルキナーダ(Harlequinade)』
『アレルキナーダ(Harlequinade)』は、コメディア・デッラルテの代表的キャラクター「アルルカン」と「コロンビーヌ」の恋物語を描いた、色彩豊かでコミカルな2幕のバレエ作品です。
陽気で人懐っこい道化師たちのコミカルな恋模様と、華やかな舞踊・衣装・音楽が一体となった、クラシックバレエならではの作品ですが、コメディア・デッラルテの伝統が生きる、“笑いと夢の詰まったバレエ”と言えます。
各登場人物のヴァリエーションは、バレエコンクールの定番曲としてもよく踊られているので、コンクール曲としてのイメージが強いかもしれませんね。
『プルチネルラ(Pulcinella)』
『プルチネルラ』は、イーゴリ・ストラヴィンスキーが作曲し、バレエ・リュスによって1920年にパリで初演されたバレエ作品です。
コンメディア・デッラルテ出身のキャラクター、道化師プルチネルラが主役で、コミカルでウィットに富んだ物語です。
ピカソが舞台美術と衣装を担当し、独創的なビジュアルも当時は話題になりました。
作品全体が、イタリア仮面劇を現代的なセンスで再構成し、音楽・美術・演劇の融合を実現したバレエと言えるでしょう。
『カルナヴァル(Carnaval/謝肉祭)』
『カルナヴァル(Carnaval/謝肉祭)』は、ロベルト・シューマン作曲のピアノ組曲「謝肉祭(Op.9)」をもとにしたバレエ作品で、多くの振付家が舞台化してきました。
この曲は、20曲以上で構成されるミニアチュア集で、各曲には「ピエロ」「アルルカン」「コロンビーヌ」など、コンメディア・デッラルテのキャラクター名が付けられています。
仮面舞踏会の世界観と、登場キャラクターのコミカルで詩的なやりとりが大きな魅力です。
『フェアリードール(人形の精)』
おもちゃ屋さんを舞台に、人形たちが真夜中に動き出す夢のような物語です。
物語の終盤では、コロンビーヌを思わせるフェアリードールを中心に、2人のハーレキン(道化)とともに華やかなパ・ド・トロワを踊ります。
多くの特徴的な人形が個性的な踊りをしながら楽しいひとときを過ごす設定は、コンメディア・デッラルテの伝統が色濃く反映されていると言えます。
最後に
単純に『くるみ割り人形』を見る上では、コンメディア・デッラルテ(Commedia dell’arte)の知識を知っておく必要ないですが、ここで登場するストックキャラクターの性格や様式を知っておくと、鑑賞の幅が広がるのは確かでしょう。
実際に、『くるみ割り人形』の一つの演出では、人形の踊りとしてではなく
コンメディア・デッラルテの一座の者たちが余興として踊る
という設定もあります。
コンメディア・デッラルテの現代までの影響を頭に入れておくと、バレエのみならずオペラや演劇などの鑑賞にも役立ちますので、ぜひ知識として頭に入れておいてもらえればと思います。




















