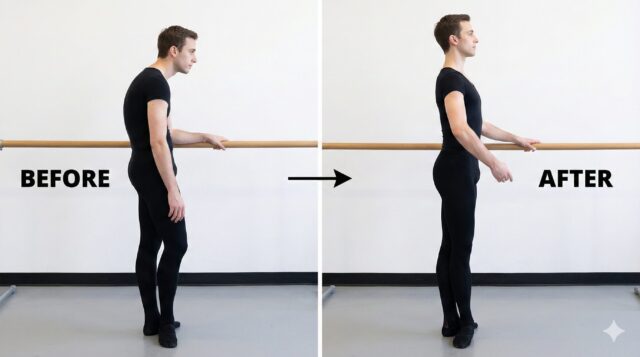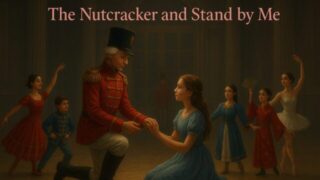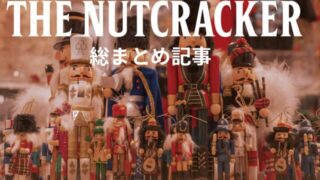オペラ『イオランタ』:バレエ『くるみ割り人形』と並んで生まれた、もうひとつの傑作(Iolanta / The Nutcracker)
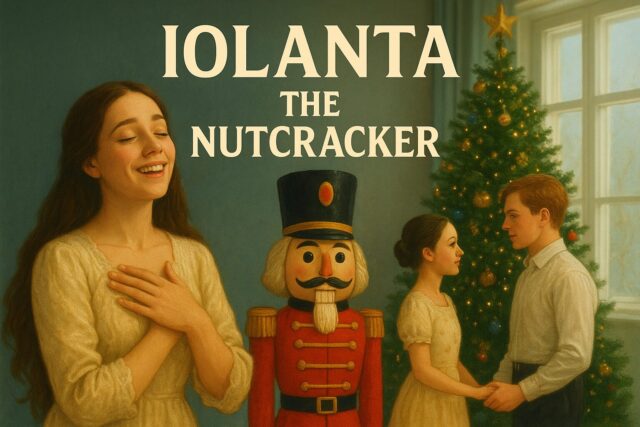
バレエ『くるみ割り人形』を語る時、忘れてはならないのが“もうひとつの同夜上演作品”、オペラ『イオランタ』です。
1892年12月18日、サンクトペテルブルクのマリインスキー劇場で行われた初演――この夜はチャイコフスキーのオペラとバレエの二本立てというプログラムでした。
前半にオペラ『イオランタ』、後半にバレエ『くるみ割り人形』。
どちらもチャイコフスキー晩年の創作であり、夢と光、無垢と覚醒というテーマを対にしたような姉妹作です。
『くるみ割り人形』が“夢の中で少女クララが成長していく物語”だとすれば、『イオランタ』は“現実の中で少女が光に目覚める物語”。
この対照関係は、まるでチャイコフスキーが意図的に構成したかのような芸術的対話を感じさせます。
今回はこのオペラ『イオランタ』を、『くるみ割り人形』との関係も含めてながらお話ししたいと思います。

『イオランタ』ってどんな物語!?
『イオランタ』(Iolanta)は、ピョートル・チャイコフスキーが1891年に作曲した全1幕のロシア語オペラで、作曲者最後のオペラ作品です。
台本は弟のモデスト・チャイコフスキーによるもので、デンマークの劇作家ヘンリク・ヘルツの戯曲『ルネ王の娘(Kong Renés Datter)』を原作としています。
舞台は15世紀の南フランス・プロヴァンス地方。
主人公の王女イオランタは、生まれつき盲目であるにもかかわらず、そのことを知らずに育てられています。
父王ルネは、娘が「自分は見えない」という真実を知ることを恐れ、外の世界から彼女を隔離してきました。
物語を動かすのは、名医エブン=ハキヤです。
彼はイオランタの病を診察し、こう告げます。
治療は可能だ。しかし、本人が“光を見たい”と強く願わなければ、決して治ることはない。
この“心の意志”が物語の核心です。
やがて、偶然訪れた騎士ヴォーデモンとの出会いによって、イオランタの世界は動き出します。
彼との会話を通じて初めて「光」「色」「美しさ」という概念を知った彼女は、自分が何かを「知らない」ことに気づき、見たいという願いを抱きます。
そして父王は、娘を守るための嘘をやめて、真実を伝える決心をします。
最後には、イオランタが「見たい」という強い意志によって視力を得て、光の世界と愛に包まれて幕が閉じます。
「強い意志がなければ治療できない」
この台詞を口にするエブン=ハキヤは、単なる医者ではありません。
彼は
人の魂と身体は不可分である
という、極めて哲学的な真理を体現する人物です。
どれほどの医学的知識や技術があっても、患者自身が「治りたい」と望まなければ、奇跡は起こらない――この考え方は、後世の文学や医療ドラマにも通じる普遍的なテーマです。
たとえば手塚治虫の『ブラック・ジャック』にも、同じような思想が繰り返し描かれていました。
医師がどんな手を尽くしても、最終的には「生きたい」「治りたい」と願う本人の意志がなければ回復は叶わない。
『イオランタ』もまた、その心の「覚醒」をドラマの中心に据えています。
この「心の光」が見えた瞬間、イオランタの世界は暗闇から一気に色彩を帯び、音楽もそれに呼応して輝きを増します。
終幕の合唱「光への賛歌」はまさに、精神的な癒しと再生の音楽的象徴です。
おすすめDVD ⇒ パリ・オペラ座上演版
『イオランタ』の上演は毎年クリスマスシーズンに上演される『くるみ割り人形』ほど頻繁ではありませんが、現在でも上演されています。
YouTube動画でも見ることができるし、DVDでも販売されていますが、日本語字幕のあるものが少ないのが、日本人には痛いところかもしれません。
日本語字幕のあるDVDなら、2016年のパリ・オペラ座で上演されたもの(演出:ドミトリー・チェルニャコフ、指揮:アラン・アルティノグリュ)がオススメです。
この演出の面白いところは、『イオランタ』は『くるみ割り人形』の主人公マリー(クララ)の誕生日パーティーで家庭劇として上演されている設定としているところです。
その後に続く『くるみ割り人形』の劇中劇形式にしていることで、両者の作品を不可分なものとして扱っています。
オペラとバレエを融合させ、両演目の物語的・テーマ的つながりを強調しており、別々のストーリーではなく一つの作品として仕立て上げているところが面白かったです。
ただしバレエに関しては従来の演出とは異なり、かなりコンテンポラリーになっています。
音楽の順序は一応チャイコフスキーの順序どおり進みますが、くるみ割り人形や王子や金平糖の精などは出てこないし、振付もかなり現代的になっています。
プロジェクションマッピングを多用したりして、映像として綺麗なところもあるのですが、オーソドックスな『くるみ割り人形』を期待しているとかなり幻滅するので注意してください。
パリ・オペラ座は伝統を重んじているように見えますが、たまにやけに急進的な作品も放り込んでくるので、ある意味そこが一番興味深かったです。
バレエはともかく『イオランタ』に触れてみる上では、入りやすい演出なので興味がある方は見てみるといいでしょう!
最後に
『イオランタ』と『くるみ割り人形』――この二つの作品は、同じ夜に生まれた「夢と光」の対作品と言えます。
ひとつは無垢な少女が夢の世界を通して大人へと成長していく物語。
もうひとつは、盲目の少女が真実の光を知り、内面から覚醒していく物語。
どちらのヒロインも、自分の世界の境界を越えようとする勇気を持っています。
そしてその勇気こそ、チャイコフスキーが最晩年に描きたかった魂の成長の象徴なのかもしれません。
バレエファンにとって『くるみ割り人形』は冬の風物詩ですが、その隣にはいつも静かに光るもうひとつの宝石――オペラ『イオランタ』があることを覚えておいてもらえればと思います。